身体を冷やしやすい食品
- 元貴 浅野
- 2024年12月15日
- 読了時間: 4分
更新日:2024年12月18日
こんにちは、今回は前回の続きで、身体を冷やす食品についてをお話していこうと思います。
前回のブログの内容はこちらへ。
夏場には身体を冷やす食べ物は良いかもしれませんが、冬場には逆効果になってしまいます。
季節ごとに食品を意識をしていただき、身体を健康に保ちましょう。
目次
身体を冷やしやすい食品
・砂糖(上白糖)
砂糖(上白糖)は身体を冷やしてしまう働きがあります。
砂糖はいろいろな食べ物に含まれていますが、精製の過程でビタミンやミネラルが取り除かれ白くなっています。そのために「単糖」となり単純に甘いと感じます。
逆に「黒糖」や「てんさい糖」は身体を温める糖と言われています。
これらの糖はカルシウムや鉄や亜鉛などミネラルが含まれているので、胃腸の働きも良くするために身体をあたためます。

・飲み物
寒い時期には、温かい物を飲みたくなります。
しかし、身体を冷やしてしまっては意味がありません。
身体を冷やしてしまいやすい飲物は・・・ずばり緑茶です。緑茶に熱を取る作用があり、頭の熱でののぼせを取ってくれます。また、カフェインが入っているので利尿作用があり、水分を排出して体温を下げる作用があります。
お茶の中でも紅茶は逆に温める作用があります。作る工程で発酵が入るので体を温めるとされています。

・夏の食べ物
夏の食べ物といえば、夏野菜、夏の果物スイカなと思い浮かべると思います。
東洋医学では、暑い地方や暑い地域で育った物が「陰性」の食べ物と考えられています。
食事で体温調整するには、季節の物を昔ながらの調理で食べるのが良いので、暑い時期に取れる物は基本身体を冷やすと考えても問題ないかと思います。
また、唐辛子やカレーなど辛く汗の掻きやすい物は一時的に体温を上げますが、汗で体温を下げてしまう可能性がありますのでご注意ください!(ほどほどに)

身体を冷やす食品まとめ
炭水化物:小麦、大麦、ハト麦、そばなど
野菜:トマト、きゅうり、なす、レタス、キャベツ、小松菜、大根、たけのこなど
果物:梨、スイカ、メロン、りんご、いちご、キウイフルーツなど
乳製品:バター、ヨーグルト、アイスクリームなど
調味料:塩、しょうゆ、砂糖など
飲物:緑茶、ウーロン茶、ジャスミン茶、プーアル茶、ハイビスカス茶、清涼飲料水(ジュース)など
まとめ(冬の過ごし方)
昔の人は、季節に合った食事や食べ物を食べることによって生活してきました。
現代社会では、季節にかかわらず食品が並んでいます。
季節感のない食事は、身体の生命力を低下させる可能性があります。そのため気持ちが落ち込みやすくなったりして、冬の時期では「冬季うつ」になったりします。
冬季うつの予防するために理想的な過ごし方は、身体を徹底的に温めて、生命力の低下を防ぐのが良いでしょう。
また、規則正しい生活といえば早寝早起きが基本ですが、冬は早く寝て少し遅く起き体力を温存します。寒い時期は起きるのが難しいですが、早く寝るようにして睡眠時間を多く取るように心がけましょう!
冬の臓器は「腎」。東洋医学では、成長や生殖、若さを担う臓器とされています。
冬の冷えは万病の元であり、腎が冷えると生命力が低下してさまざまなトラブルが発生します。たとえばドロドロ血があげられます。身体が冷えると、排泄臓器のはたらきが落ちて代謝が悪くなるため、身体の中の老 廃物が排泄できず、血液がドロドロになりがちです。また、血圧も上がりやすくなります。
冷え性の方はとにかく温めること。3つの首といわれる首、手首、足首を、マフラーやレッグウォーマーなどを活用して集中的に温めましょう。外気に触れる太い血管を温めることで体温の低下を防ぎ、温かい血液を手足の先まで届けることができます。
とくに注意したいのが腰の冷えです。生命力の元となる腎にストレスがかかるので、腹巻きやカイロを活用して温めることが非常に重要です。
冷え対策にうってつけなのが入浴です。シャワーだけで終わらせるのではなく、ゆっくりと湯船に浸かって温めましょう。
生命力が高まる食材には、黒豆や黒ごま、黒きくらげ、玄米、海苔などの海藻類、なまこ、なめこ、山芋など、色の黒いもの、ネバネバしたものが知られています。
冬は生命力の低下に直結し、とくに春に不調が出やすくなります。逆にいえば、冬は冷え予防を徹底することで、生命力を高めることができる季節。身体を冷やさないように過ごしましょう。
冬過ごし方のポイントまとめ
早く寝て少し遅く起きて体力を温存する。
首、手首、足首を温める。
腰を冷やさないように注意する。
湯船に浸かって身体の芯まで温める。
温かい食べ物を取る。


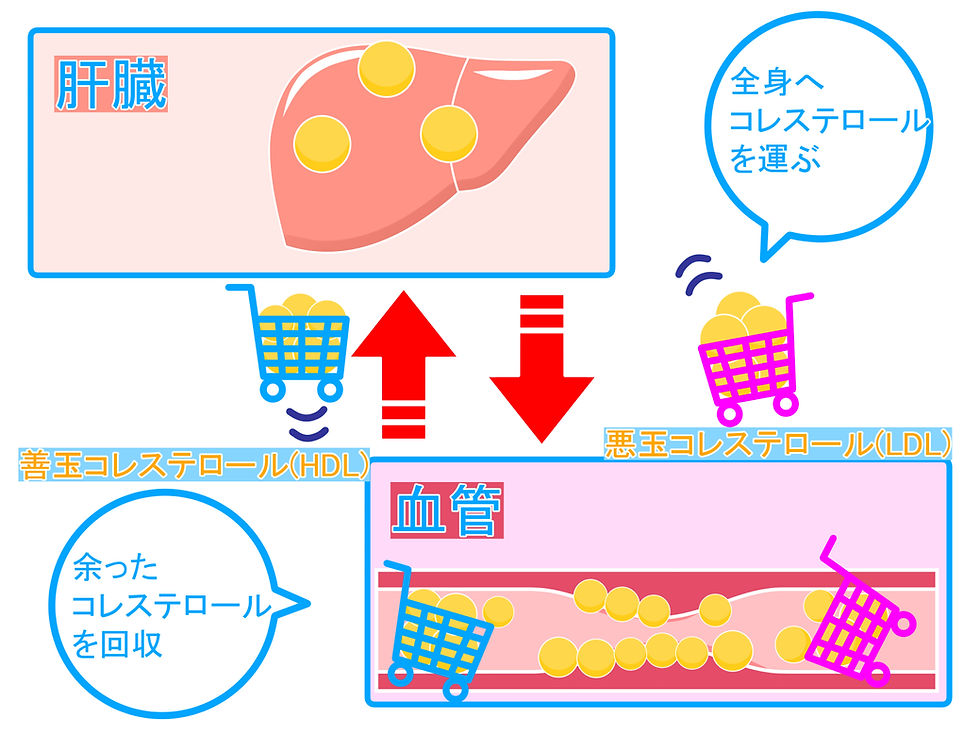

コメント